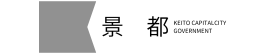『次はー鉱金、鉱金終点です。KR外環状線、景都都営地下鉄線はお乗り換えください。
本日も景王電鉄をご利用いただきましてありがとうございました』
と、車内放送が鳴り響くと、明雲義導はふと顔を上げた。
窓の外を見ると行きの景色とはまるで違う都会の風景が広がっている。
自宅を出て電車に揺られること50分。車窓に映っていた静かな住宅街や畑の風景は、いつの間にか、高層ビルが立ち並ぶ都会の光景へと移り変わっていた。
やがて電車がゆっくりと停車すると、周囲の乗客が一斉に立ち上がり出口へと押し寄せて行く。それはまるで、世間が注目している殺人事件の裁判で判決が下された瞬間、傍聴席にいたマスコミが我先に速報を伝えるべく、一斉に席を立つような慌ただしさだった。
義導はその様子を横目で見ながら、開いていた参考書をリュックに仕舞うと、乗客が皆車両から出払った頃合いで漸く立ち上がった。頭の中は明日に控えた司法試験のことでいっぱいだ。
ゆっくりとホームへ降り立つと、一日平均利用者数200万人を超える人の営みによって形成された、生温かい都会独特の臭いが景都への来訪を歓迎する。
(この臭いを嗅ぐと都心に来たって感じがするよな)
義導が久々の景都に内心ウキウキしていると、タイミングを見計らったかのようにポケットの中で携帯が震えた。
画面を開くと映っていたのは電話帳に唯一登録している恩人の名前だった。
「——はい、明雲です!」
『いよいよだな。義導』
「山下先生! ご無沙汰してます」
落ち着いた声で話す電話の主は「山下一義」弁護士をしている義導の恩人だ。
『その様子だと体調は万全のようだな。周りが騒がしいようだが今、外か?』
「はい、景都内で前泊しようと思ってて、丁度今、鉱金に着いたところです」
『ほう、お前にしては準備がいいな。アテはあるのか?』
「いえ全く。とりあえず改札降りたら近くのネットカフェで前泊しようかなー、ってあれ?」
『どうした?』
「……norica落としちゃったかもです」
その後、激励の電話が説教の電話になったことは言うまでもない。
「はは、出先の電話で良かったー」
あれから5分ほどであったがコッテリ絞られた。しかし外にいたお陰で説教はすぐに済んだ。
もし家にいれば3時間コース。対面していれば4時間コースだったと思えば運が良い。
説教の内容は、電車の清算に使うICカード「norica」を落とした件から端を発し、ネットカフェで夜を凌ごうとしていた件についても絞られた。
普通なら血の繋がりのない赤の他人に、そこまで言われると煩わしく感じてしまうだろう。
しかし、義導はそうは思っていなかった。寧ろ感謝の念すら感じているくらいだ。
山下一義は、昨年まで義導の未成年後見人を務めていた男である。16歳の時に両親を事故で亡くし孤独に陥った義導の世話を引き受けていた。
一義からすれば弁護士業の一環としてただの仕事として割り切ることもできたはずだが、そうはしなかった。
義導が受けた悲しみを共に背負い、士業の範囲を超えて彼を支える覚悟を引き受ける前から決めていた。
道に迷った時は優しく諭し、間違ったことをすれば時に叱り、彼の親代わりとなったのだ。いや、それ以上かもしれない。
そもそも、義導が法曹界を目指すようになったのも一義の影響だ。あの人の背中を追いかけたいと思った。自分も、誰かを支えられるような存在になりたいと。
かくして、義導と一義の間には親子同然の絆が通っているのだ。
そんな一義の説教はこのように締め括られた。
落としたnoricaについては、駅構内にある「忘れ物センター」なる施設をあたれと。前泊の宿泊先については「俺の事務所に来い」と。本当に頭が上がらない。
(とはいえ僕ももう18だし。後見人プログラムも終わってるのに、いつまでも先生の世話になるのもダメだよな、自立しないと……)
義導は感謝と情けなさを胸に宿しながら反省すると、なけなしの現金で電車賃を精算して改札を抜け、一義の指示に従い鉱金駅1階の隅っこにある「忘れ物センター」にやって来ていた。
「すみません、落とし物の確認をお願いしたいんですが」
自動ドアをくぐり入室すると、客と駅員の境界を区切るように受付のカウンターが立ちはだかっており、その真ん中で覇気のない中年の男性駅員がたった一人で業務を切り盛りしていた。
畳で言えば4畳分ほどの広さだろうか。都心のターミナル駅にある施設にしては、随分手狭な部屋……という印象で、室内には所狭しと棚が並び、雑多に積まれた落とし物が埋もれている。
「はいはい、どうぞこちらへ」
幸い他の客はおらず、すぐに対応してもらえた。のだが——
「お客さん。青いパスケースに入ったnoricaは届いてないねー」
「あー、はは……ですよね」
狭い空間に気まずい空気が流れる。とはいえ義導自身薄々見つからない予感はしていた。
無くしてからそう時間も経っていないので、落とした場所に鎮座しているかもしれないし、そもそも無記名式のnoricaなので、届かずにそのままパクられて泣き寝入りなんてことも、センターへ向かう道中想定していた。
「もし届いたら連絡するから念の為、名前と連絡先を教えてもらってもいいかな?」
と、中年の駅員さんに言われると、義導は渡された用紙を受け取りながら「わかりました」と返事をし、記入した後に返却する。
「うん、確かに。では何かあればまた連絡します」
「はい、よろしくお願いします」
と、お互い内心では「届くわけない」と思っている約束を、社交辞令的に済ませると、義導は軽く会釈し駅員に背中を向けたその時だった——
——キィィィィィィィィィィィン
突然、構内のスピーカーから甲高い金属音のような音が鳴り響いた。
「——ハァッ、何……今の?」
あまりにも耳障りな音に思わず耳を塞いでいた義導は、鳴り止んだことを確認すると、駅員の方を振り返り冗談混じりに話しかける。
「いや〜ハウリングでもしたんですかね〜……って、駅員さん?」
振り返ると明らかに苦しそうな表情で蹲り、身悶えしている駅員の姿がそこにあった。
「グッ……うぅ」
「え、大丈夫ですか!?」
義導は、駅員の異変を察知するやいなや、受付のカウンターを乗り越えて彼の元へ駆け寄った。試験に備えて持って来た参考書や六法全書、着替え等々の詰まった大切なリュックをその場に全部かなぐり捨てて。
駆け寄ってすぐに右手で駅員の首筋に触れると、脈拍は不規則な打ち方をしていた。素人目に見ても分かるくらいに——
「これは救急車呼ぶべき……だよな」
そう自問自答すると、スラックスのポケットから携帯を取り出し、汗ばんだ手で『119』と入力しコールする。
——電話はすぐに繋がった。
『はい、119番。火事ですか? 救急ですか?』
「救急です!」
『住所を教えてください』
「景都市内鉱金駅構内1階にある忘れ物センターです」
『どなたがどうしましたか?』
「鉱金駅の駅員さんが急に蹲って苦しんでいるみたいで」
『あなたの名前と連絡先を教えてください』
「明雲義導と申します。連絡先は——」
出たのは若い女性の指令員だった。声がよく通っており聞き取りやすい。
質問の仕方は的確でありながらも簡潔で、そのおかげかパニックを起こすことなく不思議と冷静さを保ちながら回答できた。
だが、安心感を覚えたのも束の間。そう長くは持たなかった。
「グアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!」
さっきまで蹲っていた駅員が突然大きく身をよじらせながら苦しみ出したのだ。発せられた呻き声は声量もトーンも人間の喉から出てきたものとは思えない音だった。
呻き声は電話越しでも聞こえていたらしく、指令員が『どうされました?』と様子を伺う。
「駅員さんが突然大きく苦しみ出して……ってこれは……」
義導は状況を補足するべく駅員に目を向けると、そこに映った異様な光景に絶句した。
「駅員さんの頭部が……管のようなものに覆われて……いや、生えている……?」
駅員の頭部から血の混じった粘液を撒き散らしながら、無数の細長い管が突き出ていたのだ。その管は生き物のように蠢き、先端がまるで呼吸をするように脈動している。
義導はしどろもどろになりながらも自分の持ち合わせている語彙力を振り絞って、この異様な光景に合う言葉を探しながら何とか口頭で伝えていた。だが、言葉を選んでいるうちにも駅員の変化は止まらず、ついに管は頭部だけに留まらず身体全体をも覆い尽くしていった。
さらにいつの間にか身体は一回り大きくなっており、その影響で服は張り裂け、剥き出しになった皮膚の色は青黒く変色している。
わずかに骨格だけ人間時代の面影を残しているが、腕と脚が伸びた影響で直立二足歩行を維持できなくなっており、身体を手足で支えていた。
その頃には、もはや人間とは呼べない存在になっており、義導も言葉を失っていた。
『明雲さん! あなたは無事ですか!?』
無言になっていた義導に危機を感じたのか、指令員が彼の安否を心配する。
しかし、義導の応答はなかった。いや、できなかったのだ。
「ガ……はッ」
駅員が義導の穴という穴に管を刺し込んでいたからだ。
鼻の穴、耳の穴、目、口、そしてヘソ。
それぞれの管はその穴から入って行き着くところまで通されており、義導は助けを呼ぶことも激痛に声を上げることも涙を流すことさえも許されなかった。
「ぐジュルルルるる」
駅員が奇声を上げながら、管で繋いだ義導の身体を持ち上げる。
彼の肉体は抵抗の意思なく簡単に持ち上がった。手足は力無くだらんと垂れ下がり、携帯は床に無機質な音を立てて滑り落ちる。
『っ! 明雲さん!? 明雲さん!!?』
電話口では指令員が必死に呼びかけていたが、彼の耳には届かない。
やがて彼女の応答に対して返ってきたのは、何かを「じゅるじゅる」と啜っているような音だった。
『……何? 何が起こっているの……?』
この時、義導の意識は既に闇に落ちていた。
落ちる直前、彼の脳裏には明日への未練と恩人の顔がよぎったという。
◆
『……義導は、鉱金にいる』
電話口でその言葉を聞いた時、全身の血の気が引いていく感覚に襲われた。
「なっ……嘘でしょ? 弁護士さん!」
『5分前にあいつから電話で聞いた情報だ。嘘ではない』
「彼との連絡は!?」
『今、別の電話で掛け直しているが繋がらない。どうやら話中のようだ』
——恐らくこの頃、すでに義導君はバイオローグに襲われていた
頭の中で導き出していた最悪の予感に蓋をしたままここまで来たが、現場を目の前にした今、その予感は認めざるを得なかった。
と、回顧する青年は、お面の奥で下唇を強く噛み締めた。
全身を黒いローブで身を包み、顔は縁日で売られているような特撮ヒーローのお面で覆い、背中にはヤケに年季の入った黒い布地の鞘袋を背負っているこの男は、景都鉱金駅構内で突如起きた未曾有の事件を止める鍵となっていた「明雲義導」に接触する為に、構内にある忘れ物センターに今しがた辿り着いたところだった。
センター内は、獣が通り過ぎたかのように汚く蹂躙されており、血生臭いニオイがお面越しでも分かる程に鼻を刺す。壁や床は血液や体液で染まり、特に汚れの激しい血溜まりの付近には臓器を抜かれた1体の肉塊が転がっていた。
「義導……君」
遺体は身元の判別など付かない程の損傷をしているが、その男は遺体の頭部に生えている赤茶の頭髪からその身元が義導のものであると判別できた。
念の為、うつ伏せの遺体をゆっくりと仰向けに起こして表情を確認するも、眼球を抜かれ土色に変色した遺体の顔に生前の面影を感じることはできず、その凄惨な状態にただただ言葉を失ってしまう。
——ブーブーブブッブーブブッブー
そんな折、突如不規則なバイブレーター音が重く冷たい静寂を破る。その音と振動はローブの懐から発せられた。
「……ッ」
弁護士「山下一義」からの着信だ。用件は間違いなく義導君の安否確認。
——ブーブーブブッブーブブッブー、——ブーブーブブッブーブブッブー
だが、出られない。いや、出たくない。
親代わりを務めていた人に「間に合いませんでした」なんて伝えられる訳がない。彼に何て言葉で伝えて、なんて言葉で謝罪すればいいのかわからなかった。
——ブーブーブブッブーブブッブー、——ブーブーブブッブーブブッブー、——ブーブーブブッブーブブッブー、——ブーブーブブッブーブブッブー
着信は鳴り続ける。青年は地面に膝を突き「止まってくれ」と心の中で祈るようにうな垂れていた。
その後、計15コールが鳴ったところで音は鳴り止み、辺りは再び静寂になった。
「すまないっ……弁護士さん」
再コールが起きないことを察すると漸く青年は言葉を溢す。
そして少しの沈黙の後、お面の下縁に指を掛けると、僅かな摩擦音を立てながら滑らせるようにお面を顔から外す。外した拍子にフードもずるりと肩まで滑り落ち、隠されていた灰髪が露わになるも、青年は構うことなくそのまま瞼を閉じ、黙祷を捧げた。
黙祷の最中、青年の脳裏には義導への弔いと同時に、喫緊の課題への対処を勘案していた——
『グロリアス・イブ』
武装組織『エルジーム』が失われた栄光を取り戻す為に起こした儀式……とは名ばかりの"テロ"である。
その内容は、景都に住まう人々を『バイオローグ』と呼ばれる異形の怪物に変え、群衆を襲わせ、自分達は一切の手を汚さずに虐殺を達成する非人道的な謀略であり、青年はこの謀略を食い止めるべく景都へ駆けつけ、明雲義導との接触を図ろうとした。
しかし、彼は既にテロの巻き添えを食らい命を落としていた。これは組織に対抗する術を失い八方塞がりになったことを意味している。
正直言って事態は最悪と言わざるを得なかった。現代兵器が通用しないバイオローグに有効な唯一の武器『剏剣』を扱える者は、こちら側の人間では明雲義導ただ一人だったのだから……
(俺がテロの予兆を掴めていれば、こんなことには……)
今は悔やんでいる場合ではない。そんなことは分かっているが、どうしても頭に浮かび上がってしまう。青年は浮かぶたびに頭を振って後悔の念を消し去ったが、それはまるで浴室の鏡に浮かぶ曇りのように、消しては現れ青年の頭を曇らせる。
(ッ、無理に消すのはやめだ……受け入れろ)
中々、消し切れない青年は、やがて諦めたかのように心の中でそう呟いた。すると、不思議と悔恨の主張が収まっていくのを感じた。払拭しようとしていた感情を、ただそのままそこに置く。そうすることで逆に意識が逸れて、思考に集中できるようになったのだ。
(バイオローグは義導君の内臓を吸っている。ということは……いやしかし仮にできるとしても、彼を殺した個体を見つけるにはどうすれば……)
集中して間もなく、青年の脳内には不確定ではあるが一つの打開策が生まれていた。だが、その過程で新たな課題が浮かび再び頭を悩ませる。
すると、青年は手がかりを求めるかのように閉ざしていた瞼を開き、藁にも縋る思いで辺りを見回し始めた。
壁、床、遺体——視線を次々と移動させながらも、青年は答えに辿り着く道筋を見つけられずにいた。次第に焦燥感が胸をかき立てる中、ふと天井に目がいくと、そこで遂に天啓を得る。
「防犯カメラ……これだ」
あれから青年は再びお面を装着すると、足早に駆け出し、駅構内の中枢エリアに侵入していた。フードは被らずに灰髪を露わにしたままだ。本当は身元を隠す為にも被っておきたかったが、多少なりとも後方の視界を確保しておきたい、そんな妥協的な判断だった。
構内は依然バイオローグが跋扈しており、本来行き交っていた人たちは、義導と同様中綿を抜かれた人形のような状態にされて、通路の至る所で力尽きていた。
物陰に身を隠しながら進む道中、そんな惨状を目にする度に自分の非力さを呪い、奥歯を噛み締めながら怪物の死角を通り過ぎていく。
そして今、青年は目的地である「中央管理室」の扉前に立っていた。
「ここ、なのか?」
管理室に繋がるドアは、古めかしい造りだというのに依然健在で、ドアとしての役目を果たしており、中の様子を窺い知ることはできない。これだけの事件が起きていると言うのにだ。それはつまり……
(この部屋はまだバイオローグに襲撃されていない……!)
バイオローグにドアを開ける程の知性はない。出入りするなら破壊する筈だ。青年はこれまで見てきた惨状と現場へ来る前に得ていた情報からそのように推理すると、胸の内に渦巻くざわめきを感じながら、ゆっくりとドアノブに手を伸ばした。
ドアノブを握る手に自然と力が入る。冷たかった筈の金属は、彼の胸中に陽炎の如く湧き上がった希望と使命に燃える心に伝導したかのように熱を帯び始める。
(せめて、中の人たちだけでも……救う)
決意が沸点に達すると、掴んでいたドアノブを右に回す。ガチャリと回して開けたその時! 一発の閃弾が自身の脳天目掛けて飛び込んで来た——
「——ッッ!!」
青年は咄嗟に身体を右に振って弾を避け、扉脇の壁に背中を預ける。
彼に向かって放たれた閃弾は、お面の縁を掠めて向かいの壁に着弾すると、破砕音を響かせながらコンクリート壁をボロボロに撃ち砕いた。
「ッ……」
青年がその光景に表情を強張らせ右肩に微かな疼きを感じていた時、不意に視界がクリアになる。
お面の弦が切れたのだ。気づけばお面が顔から離れ、ハラリと床に落ちていた。
「ほう、今のを反射で躱すとは……やるな」
青年がほんの数センチズレていたら蜂の巣になっていた状況に戦慄していると、閃弾が放たれた方向から男の声がした。
「……」
青年はその声には応じず、意識のみを声のする方へと向ける。
「それに比べてお前は使えねェなァ、貴重な一発を無駄にしやがって……まあ、平和ボケした一般愚民ならそんなもんか」
だが、その言葉を聞いた瞬間、思わず「ハッ」と壁から抜け出し部屋の中へ侵入してしまう。嫌な予感が彼の身体を突き動かしたのだ。
「ッ、何てことを……」
侵入すると、初めに出迎えたのはヌルい殺気と強烈な圧迫感だった。確かにバイオローグはいない。死体も見当たらず今まで見てきた構内に比べて遥に清潔感のある空間だ。しかし中で行われていることは異常だった。
「ひ、ひぃ」
先程の閃弾はここで働く駅員が撃っていたのだ。
駅員は部屋の中央でおぼつかない手付きで依然銃を構えている。その照準は未だ自分を捉えていたが、照準に覚悟が感じられなかった。
それもその筈、その駅員は背後の男に脅されてそうせざるを得ない状況に追い込まれていたのだ。額に流れる冷や汗や、引き攣る表情は恐怖と混乱の色を濃くしている。
「もう一度だけチャンスをやるよ。今度は的がよく見えるだろ?」
そう言って駅員に命令しているのが、壁越しに聞いたあの男だった。男は駅員の後頭部に拳銃を押し付けて完全に手玉に取っている。
「そ、そんな、嘘だろ。頼むから解放してくれ」
だが、駅員は自身の倫理観に従ってその命令を拒んだ。その様子を目にした時、最悪の展開が青年の頭をよぎる——
「——ッ! よせッ!!」
(本気で殺す気のない銃は俺には効かない。だから構わず撃ってこい! こんなイカれた奴の指示を拒んだりしたら……)
気づけば身体が勝手に動いていた。脳裏によぎった展開を回避するべく一気に間合いを詰めに行く——
「しょうがねぇな。じゃあ解放してやるよ……現世からな」
しかし、青年の願いは叶わない。男は引き金を引いて駅員の頭を容赦なく撃ち抜いた。
「」
駅員は悲鳴を上げる間もなく額から血を噴くと、糸の切れた人形のように力なく崩れ落ちていく。
「——クッッ」
駅員を助けるべく割って入ろうとした青年は、勢いをそのままに重心を低く落として滑り込むと、地に伏せる寸前だった駅員を間一髪で受け止めた。
「おい! しっかりしろ!!」
青年は駅員を受け止めると抱き抱えた状態でその場に屈み、必死に声を掛けた。しかし応答はない。
「おいおい、コイツが即死なことくらいお前程の人間ならわかるだろォ?」
代わりに応答したのは駅員を殺した張本人だった。
曼荼羅模様の柄シャツに色褪せた白衣を羽織ったその男は、細長い金縁メガネを軽く押しながら小馬鹿にしたように話しかける。
その様子は罪悪感を一切感じていない、まるで蚊を潰しただけのような1ミリも気に留めていない様子だった。
「ハヴィル・アインス......」
「ほう、俺を知っているか。俺はお前を知らないが……その格好を見るに、同胞だな?」
「……直接的な殺害はしないんじゃなかったのか?」
青年はハヴィルの質問には答えずに、温もりを失っていく駅員の体温を掌で感じながら、ワナワナと震えた声で別の質問を投げた。
「バイオローグの発生と一連の殺戮行為を自然発生的な現象に装うべく、俺たちは直接的な殺害はしないって決めてた話のことか?」
ハヴィルは青年の態度に一瞬眉をピクリと動かしたが、そのまま話に乗っかった。
「この部屋に1体でもいればその通りになっていただろうが、生憎誰も変異しなかったみたいでねェ。まァ部屋の外に出したところでどうせ死ぬ運命だろうし、結果は同じだろう? それに、この部屋なら多少の事象は改竄できそうだしなァ」
と、嘲笑ったかのように回答すると、机上のコンピュータをトントンと叩いた。
「いや〜、にしてもここに来るまでの間、警察がこんなおもちゃみたいな銃でバイオローグに挑んでいるところを見ちまって思わず吹き出しちまったぜェ」
愚弄の弁はまだ止まらない。ハヴィルは思い出し笑いをしながら駅員を撃ち抜いた拳銃を青年に見せつけるかのようにチラつかせると、手の中でクルクルと回す。恐らく鉄道警察が所持していたものを拾ったのだろう。
この男の言動と行動に青年もいよいよ沈黙を保てなくなり、悲憤に満ちた感情を滲ませながらゆっくりと口を開く。
「ここまで性根が腐ってると返す言葉も見つからないな」
「おいおい、そこまで言うなよ。この哀れな駅員さんにも、少しくらい情けをかけてやれって」
だが、ハヴィルはその皮肉が自分に向けて言われていることを理解していなかった。いや、それとも理解した上で青年の心を掻き乱す為にわざと曲解したのだろうか? 腹の底は見えないが、つくづく人の神経を逆撫でさせる男であることは間違いない。
そう冷静に分析しているように見えて、青年の心は動揺していた。自分の言葉が悪用され、意図せず駅員の侮辱に加担させられた罪悪感にじわじわと心を侵食される。それはまるで仕事や役割を全て取り上げられて自己を無力化されたところに、根も歯もない悪評のレッテルを貼られたような気分だった。
「でも、まああれだな『性根が腐ってる』ってのはお前の方が当てはまるんじゃないのか?」
「……何が言いたい?」
ハヴィルは青年の隠しきれていない動揺の色を見て、不敵な笑みを浮かべると、諭すように答え始める。
「組織が厳重に保管していた『剏剣』を盗み、あろうことか非力な愚民に使わせて、そのままそいつを戦士に仕立て上げて、一国の命運をそいつ1人に押し付けようとしてたんだよなァ?」
「ッ!」
ハヴィルの思い掛けない発言に、青年の心臓がバクンッと音を立てた。
計画がバレている——いや、それ以上に「押し付けようとしていた」という歪んだ解釈が許せない。しかし「そんなつもりではない」と弁明すれば、同時にヤツの推理を認めてしまうことになってしまう……
そう考えると青年は何も言えなくなってしまった。そこにハヴィルのさらなる追撃が入る——
「『推理』なんかじゃねェよ」
跳ね上がった心臓を一突きされたような一言だった。完全に思考を読まれている。
「ククッ——お前、まさか隠せてるつもりだったのか?」
「なっ……まさか」
「バレてるに決まってるだろ。末端の構成員如きが組織全体を騙せると思うな」
ハヴィルが告げた真相は、青年にとって非常に酷なものだった。何しろ既に犠牲者が出ているのだから。
「バカな! じゃあ、この剏剣はわざと盗ませたっていうのか!?」
青年は先の思考など吹っ飛んでしまい、背中に背負った黒い鞘袋をチラッと見ながら我を忘れて問い掛ける。
「当たり前だろう。何だ? まさか組織の警備を掻い潜って勝ち誇った気でもいたのか? ククッ、そういうのを『驕り』って言うんだぜ」
その言葉に青年は耳を疑った。
「待て、それにしてもおかしいだろ!? 何でお前らの目的の邪魔になる可能性を許したんだ!? 剏剣を盗ませるなんて回りくどい真似をする必要があったんだ……? 末端の構成員1人が剏剣を盗んだところで都民の虐殺は問題なく遂行できると思ってたのか……!?」
「その認識がそもそもの誤りだ。今回の目的はお前に掛かっていた裏切りの疑惑を確かめるところにある。その為にバイオテロを起こす筋書きを立て、お前の動向を観察した。景都民の虐殺は副産物だ」
「は……?」
「つまり、景都の人間が怪物になったのも惨たらしく大量に死んでいったのも全部お前のせいってことだ」
ハヴィルは顔をずいっと近づけ、息が掛かりそうな至近距離でニカっと笑いながら、酷な現実を冷たく言い放ち、青年の理想をブチ壊した。
「俺の……せい?」
顔から色が抜けていく青年の顔を横目に、ハヴィルは冷たくなった駅員の胸ポケットからタバコとライターを抜き取ると慣れた手付きで火を灯し、煙をくゆらせ始める。
「——ふぃ、まあ、悲観するこたァないさ、多少寿命が縮んだだけだ。遅かれ早かれ侵攻は計画されていたしなァ」
ハヴィルは煙と共に吐き捨てるように言うと、タバコの箱に目を移し、どこか満足げに口元を緩めて再びゆっくりと煙を肺に溶かし始めた。
対する青年は畳み掛けるように告げられた真相に茫然自失となっていた。しかし、思考停止で現実から逃れることなど許されない。青年の意識は防犯カメラの映像を見ながらタバコを愉しんでいたハヴィルのさらなる一言で否応なく現実へ引き戻される。
「ところでェ……お前がよく連絡を取っていたヤツは今頃どうしてるんだろうなァ?」
その言葉にハッと顔を上げる。
「なぜそんなことまで知っているのか?」なんていう問いはもはや愚問だった。そう悟った瞬間に喉を詰まらせ、行き場を失った乾いた呼気だけが虚しく抜ける。
「着信、入ってたんじゃないのかァ?」
「ッ……!」
こちらを一瞥することなく続けたハヴィルの追い討ちに青年の身体は凍りつき、懐に忍ばせた携帯に伸びていた手もピタリと止まる。
(ハッタリなどではない——本当に俺は観察されていたッ……)
「何だ? 確認しないのか? 安心しろよ、電話にうつつ抜かしているところを攻撃したりなんてしねェからさァ」
ハヴィルは駅員が生前に飲んでいたものであろう缶コーヒーの飲み口に灰を落としながらニヤついた表情でそう言った。
「畜生ッ……!」
もはや従うしかない状況だった。分岐点のない敷かれたレールを走らされるように。
青年は今にも決壊しそうな自尊心を押し留めるかのように下唇を強く噛み締めると、ハヴィルに注意を払いながら携帯を取り出し恐る恐る画面を開く。
すると画面には1件の不在着信と留守録を知らせる通知が入っていた。着信に出なかったあの時、弁護士はメッセージを残していたのだ。
弁護士からのコールを利己的に無視した自分の行いを思い返し、胸にチクリとした痛みが走る。その感覚を抱えたまま、待ち受け画面から留守録の再生操作を行うと携帯を耳に押し当てた。
——短い機械音が流れるとメッセージはすぐに再生された。
『——すまない、どうやら君がいた組織の人間に私の素性が漏れたみたいだ……私が死んだとしても君は責任を感じるな。その代わり、義導だけは、頼んだぞ』
「なっ……」
メッセージの内容は事実上の遺言だった。
弁護士はいつもの冷静な口調で淡々と要件を告げていたが、その声はわずかに震えており、言葉の端々から近い未来に迫り来る恐怖の色を隠しきれていなかった。
「俺は……なんてことを」
青年は留守録を聴き終えると、携帯を地面に伏せ、自身の浅はかな選択が招いた犠牲と業を悔いた。
保身の為に弁護士への着信を無視したことで招いた取り返しのつかない業。それは、弁護士が生きている内に義導の死の報告と謝罪をできず、今後一切伝える機会も失ったこと。さらにその結果、彼の遺言を速攻で裏切り偽りの希望を抱かせたまま死なせてしまったことである。
「っさて、と。思わず涙を誘ってしまいそうなヒューマンドラマをどうもありがとう。だが、そろそろ飽きたぜェ」
青年が悔恨の沼に浸っている中、一服を終えたハヴィルが言葉とは裏腹な表情で青年の前に立っていた。右手に持っていたタバコはいつの間にか注射器に変わっている。
「続きは帰国してからだ。まアそんなことに思いを巡らせる余裕があればの話だがなァ」
何か含みを持たせるような発言をすると、ハヴィルは青年の頭を上から押さえて頸に注射針をゆっくりと近づけ始めた。青年に抵抗する様子は見られない。
「大人しくしてろよ、打ち所をミスれば永遠に目覚めなくなるからな」
テロの実行を指揮し駅員を躊躇なく射殺し、青年の精神を痛ぶって反応を楽しんでいた男だが、注射を打つこの瞬間だけはまるで熱を失ったかのように真剣な声色で青年に忠告した。
「「…………」」
注射器の先端がジリジリと近づく。青年は依然うな垂れたように頭を伏せており、ハヴィルも青年に抵抗の意思がないことを確信した。
だが、針先と皮膚が触れかけたその時、突如、注射器が宙へ飛びハヴィルの手から離れる——
「——ッ!」
刺さる寸出で青年が右手で払ったのだ。
流石のハヴィルも正確な穿刺を行うべく集中していた為か、青年の咄嗟の動きに反応できず、抵抗を許してしまう。
「テメェ!!」
その失態に激昂したハヴィルが青年の頭を地面に打ち付けようと押さえていた手に圧力を掛ける。だが、その前に青年が片膝を強く踏み込んで立ち上がり、ハヴィルの左手を押し返した。
「っ、どういうつもりだァ? テメェの身勝手でまだ罪を重ねるつもりかァ?」
「……かもな」
青年はよろめきながら立ち上がると自嘲気味に返答した。
「俺は……取り返しのつかない過ちを犯した。俺が浅はかだったせいで本来護る対象の景都の人間を死なせてしまい、俺の計画に付き合わせてしまった人も死なせてしまった。それは認めるよ」
「ほう、随分素直じゃァないか」
「だが、だからといって、アンタらの暴挙が許されるわけでもないし、止めなければならないことに変わりはない」
「業を背負ってでも。か?」
「業を背負ってでもだ。業を背負ってでもアンタらエルジームの暴走を止める。それが死なせてしまった人たちへできる……せめてもの贖罪だ」
青年はハヴィルの問いに迷う事なく言い切った。彼に問われなくても最初からそう言うつもりだったかのように。
「そりゃあ随分崇高な御覚悟だなァ」
ハヴィルは青年の覚悟を咀嚼するように聞くと、白衣のポケットをおもむろにまさぐり——
「やれるもんならやってみろよッ!!」
怒声と共に、いつの間にか回収していた閃弾を放つ銃を引き抜き発砲した。
「ッ!」
ゼロ距離射撃当たれば即死。だが、青年の動きはハヴィルの早撃ちを上回っていた。
青年はポケットから冷たく光る銀色の銃身が見えた瞬間、ハヴィルの腕を掴んで上方に持っていき、弾道を逃がしていたのだ。
「っ、駅員の時といい今の射撃といいテメェの反射神経は一体どうなってやがる」
「アンタがノロマなだけだ」
「……言ってくれるじゃねェかァ」
閃弾が新たな進行方向へ逸れて行くその刹那。両者は弾の行く末など気にも留めずに、ギリギリと組んず解れつの状態になりながら言葉の応酬を繰り広げていた。しかし、膠着状態は意外にも早く解かれる。
閃弾が天井に着弾したのだ。
となれば「その後どうなるのか?」を想定できないほど両者の頭は馬鹿ではない。天井の崩落を察知した2人は互いに舌打ちしつつ、相手の胴体を蹴って拘束を解き後方へ跳んだ。直後に天井は崩れ落ち、先ほどまで二人がいた範囲を瓦礫が飲み込んでいく。
「ったく、何つー破壊力だ……たった一発でここまで」
青年は回避に成功して得られた一瞬の猶予の中で、閃弾がもたらした惨状を目の当たりにし、思わず驚嘆の声を漏らした。
そんな閃弾を至近距離にもかかわらず無傷で躱せたのは良かったが、崩落の影響で舞い上がった塵が視界を覆い尽くし、室内の照明も死んでしまったことで優勢だった戦況は一瞬で霧散した。相手の腕を拘束していた感触も、もうない。寧ろ飛び道具を持った相手だと戦況は振り出しどころか悪化したといえるだろう。
(俺が逆の立場なら……撃つだろうな)
その読みは当然当たる。
瞬間、銃声と共に一発の閃弾が灰色の層を突き破って飛んで来る。
「……」
閃弾の軌道は的外れな方向だったのでわざわざ身をよじって躱す必要はなかったが、相手も同様に視界を奪われた状況下にしては侮れない射撃精度だった。
恐らく自分が回避した方向からおおよその場所を読んで撃ってきているのだろう。この先微かな足音や空気の揺らめきを頼りにきっとハヴィルはさらに精度を上げてくる。
(——であればッ)
青年はハヴィルの戦闘センスを内心で評価すると、来た道を戻るように先程取っ組み合ってた方角へゆっくりと歩み始めた。どうせ当たるのならば回避はやめだ——
するとハヴィルも再び閃弾を発砲した。弾道はさっきよりも正確に青年の心臓を射抜きに来る。
(どうせ当たるのならば回避はやめ……全弾凌ぐッッ)
すると青年は懐に隠し持っていたコンバットナイフを抜刀し閃弾を弾いた。
「くッッ……!」
弾かれた閃弾はナイフの刃に当たるとバチンッと電線が切れたような音と火花を出して彼方に散る。
しかし、無傷で防いだとは言えなかった。ナイフの刃に閃弾が当たった衝撃が手首から肩まで響き、ジンジンと痺れるような痛みを残したからだ。腕に残る衝撃は青年の想像以上に重たかった。
だが、青年の腕の回復を待たせないかのようにハヴィルは堰を切ったように撃ち込んでくる——
「チィッッ」
青年は追撃の一発を再度弾くと、一か八か地面を蹴って一気に間合いを詰めに行った。
正直このゴミみたいな視界で走りながら弾を見切るなんて阿呆の所業だが、だからといってこのまま悠然とジリジリ歩いて詰めて行く余裕もない。
腕の感覚からそう判断すると、視界の奥で捉えていた閃弾の残光を辿って、ハヴィルとの距離を急速に縮めていく。一発弾く度に衝撃でナイフを手からこぼさないように強く柄を握り締めて。
そして計5発程弾いた頃。青年はハヴィルのおおよその居所に察しがつく。さらにそのタイミングでハヴィルの攻撃の手が止んだ。
(——ッ弾切れか!? 叩くなら今しかないッ)
青年は好機のニオイを嗅ぎつけると、部屋の中央にある瓦礫の山を高く蹴って跳び上がり、空中でナイフを逆手に持ち替えながら狙いを定めた——ッ
——そして跳躍が最高到達点に達すると、ハヴィルがいると思われる南方目掛けて全体重を掛けるように前のめりに突っ込んでいくッッ!!
「ハアアアッッ——!!」
まるで隕石が降ってきたかのように、ズンッ! と鈍い衝撃が響き渡ると、同時に辺りを舞い視界を覆っていた塵が衝撃と共鳴して相対する二人を起点に一気に晴れる。
視界が晴れ、ハヴィルと再び相見えた時、青年は目の前に映る光景に思わず自分の目を疑った。
「ふィ、まさか末端の構成員如きにコイツを使わされるとはなァ……!」
「ッ!? なぜ、お前がそれを」
ハヴィルは青年が叩き込んだ渾身の一撃を完璧に受け止めていた。鍔迫り合いの状態で。
さっきまで持っていた筈の銃はいつの間にか刀剣に変わっており、その装備している刀剣もそこら辺の業物なんかでは無かった。
古の輝きを取り戻したかのような艶めいた赤銅色にスラッと伸びた長い刀身。それはまさしく神器『剏剣』だっ……「グハッ!!」
目の前の状況を頭が理解する前に、青年は剏剣を携えたハヴィルに勢いよく薙ぎ払われ、北方の壁へ吹っ飛ばされる。
ロクな受け身も取れずに壁に激突した青年は、そのままコンクリート壁を砕いてめり込み、崩れ落ちる瓦礫の餌食になった。
「『機剏』って言葉を聞いたことないか? エルジームのボスにしか扱えない剏剣を、部下の俺たちでも扱えるようにするべく開発が進められている武器。これが機剏だ。まァこれでもまだ試作品らしいんだがなァ」
ハヴィルは、機剏と呼んだその刀剣を肩に担ぎ、青年を吹っ飛ばした方へツカツカと歩きながら悠然と語り掛けてくる。
「でだ。ずーっと聞きたかったんだが、なぜお前は機剏に改造されていない剏剣を景都の人間が使えると思ったんだ?」
「!」
その言葉を聞いた時、不意に青年の口元が緩む。そして——
「プッ、あっははははははハッハハハハハハッハ!」
崩れた壁材にもたれかかったままツボに入ったかのように笑い出した。そして、ひとしきり笑うと一言。
「……さあ、なッ!」
返答と同時に足元にあった邪魔な瓦礫をハヴィルに向かって蹴り飛ばす。
「ほゥ」
直撃したら首の骨を簡単にへし折れる程のデカい瓦礫がハヴィルを襲うも、彼は臆することなくまるで豆腐を切るように真っ二つに一閃した。
「rrrrrrrrrrラッッ!!」
しかしそれでは終わらない。蹴っ飛ばした瓦礫を隠れ蓑に急接近していた青年がハヴィルに向かって殴り込む。
「「ッッ!!」」
二人は再び刃を交えると、今度は一撃に止まらず激しい剣戟へと発展させた。
「おいおい! いきなり笑い出すもんだから壊れちまったのかと思ったぜェ」
「まさか! 寧ろアンタのお陰で元気が出たくらいだ」
「っ——どういう意味だ?」
「計画の全貌を掴めていない癖にッ——あんなに楽しそうに論破していたアンタの滑稽さにだよッ」
——剣戟の最中、彼らは力比べだけでは飽き足らないのか、同時に舌戦も展開していた。お互いの刃が衝突する度に彼らは皮肉をぶっかけ合う。
「っ、まァ今のうちに燥いでろよ——帰国したらゆっくり話を聞かせてもらうからなァ!」
「それは叶わない——アンタはここで俺に負けるッッ」
「ふっ——そんなおもちゃで機剏に勝つ気かよ、笑わせるなァ!」
「機剏っつったって、所詮プロトタイプなんだろ?——俺のナイフと遜色ねーよッ」
「そのナイフはいつからお前の物になったんだァ? アァ!?」
「ぐッ……!」
剣幕と被せて振り下ろされた一太刀は、これまでとは段違いの重みがあった。
だが、青年も負けじと左手を刃身に添え、両手で刃を支えるようにしてハヴィルの一太刀を受け止める。そして——
「……今日この時、アンタらがテロを起こすと知った瞬間からだッ! それを止める為なら例え盗み出してでも、俺の手に……あるべきだッ——!」
そう言い返すと、そのまま相手の刀身に沿わせて刃を滑らせながら一気にハヴィルの懐に入り込み、ズバンッ! と袈裟斬りにして突っ切った。
「っ、ゴハッ……」
右肩から脇腹にかけて斜めに斬られたハヴィルは、傷口から派手に鮮血を噴き上げるもなお立ち続ける。しかしそれも長くは続かず、滴り落ちる血と共に彼の身体も地に落ちた。
対する青年はそんなハヴィルには目もくれずに奥のデスクへと向かっていた。ここに来た本来の目的を達成する為だ。
「......ハァッ、ハァッ」
デスクの前に立つと、アドレナリンで震える指先を抑えながら慣れない手付きでコンピュータを操作し、防犯カメラの録画ファイルを呼び出す。
ファイルを開くと、駅構内に設置された全防犯カメラの録画データが画面一杯にびっしりと並んだ。青年はその中から「忘れ物センター」の録画データを選ぶと、事件が起きた15時32分に映像の時間を合わせ、再生した。
『——ハァッ、何……今の?——え、大丈夫ですか!?——駅員さんが突然大きく苦しみ出して……ってこれは……——ガ……はッ』
防犯カメラは一部始終を全て記録していた。駅員が怪物へ変貌する瞬間から義導の身体に管を刺し臓物を啜るところまで。電話が繋がらなかったのは、自分が助かる為の救援通報を掛けていたからではなく、目の前の人間を救おうとする為の救援通報を掛けていたからだったということも。
時間にして一分も掛からない惨事だったが、その死に際の行動には彼の人となりが滲み出ていた。
青年は、バイオローグとなった駅員の管の隙間から垣間見える、微かに残った頭髪や制服の切れ端から義導を殺した個体を無言で目に焼き付けると、録画ファイルを閉じ、画面を血塗れのトップページに戻した。
(こんな画面じゃ、現在地の特定なんて無理だな)
当初の予定では、このまま義導を殺害したバイオローグの現在地をライブ映像から特定するつもりだったが、肝心の映像は既に大量の血飛沫でレンズを塗り潰され、使い物にならなくなっていた。一体何人殺せばこうなるのだろうか。
「……シラミ潰しに探すしかねーか」
青年は冷たく静かにそう口にすると、コンピュータに背を向けて最初に入ってきた扉へと歩き始めた……その時だった。
扉の奥から空気と水分をたっぷり含ませた不気味な呻き声が臭気を乗せて響き渡った。それも複数。
「まさか——「まさか、構内の人間、を全て‥‥殺し尽くして、此処まできたと、いうの、かァ……」
青年が口を開きかけた瞬間、同じことを考えていたハヴィルが、仰向けでヒューヒューと息をしながら被さるように代弁した。
「まだ息があったのか」
「黙、れ……小童」
ハヴィルは文字通り虫の息といった状態で戦うことは無理そうだったが、悪態に食ってかかる程度の余力は残っているらしい。
青年はそう察すると、ハヴィルの気が飛んでしまう前に聞き出しておきたいことを問い始めた。
「一応聞くが、アンタ、もし大量のバイオローグが首謀者の自分に襲いかかってきた場合の対処法とか考えてあるのか?」
「……」
「まさかご自慢の『機剏』とやらで、撤収する際に降り掛かる多少の火の粉を払えれば良いっていう程度だったとか?」
「……」
「図星かよ、随分舐められてたんだな、俺……ならしょうがないか」
青年は何も言えなかったハヴィルを蔑んだ目で見ながらそう言うと、彼の横で転がっていた機剏を拾い上げた。
機剏は、その名の如く剏剣を覆うように複数の機器類が取り付けられており、背中に背負っている生身の剏剣よりも重みがある。
「バカ、か……小僧。いくら機剏でも、その数は……無理、だァ」
「ふん、馬鹿はどっちだ。それにこっちは端からそのつもりだったんだ。寧ろ探す手間が省けたぜ」
青年は、手に持った機剏をまじまじと見つめながらハヴィルの言葉を軽くあしらうと、そのまま話を続ける。
「それよりもそんな口を叩く余裕があるなら、使い方教えろよ。ついでにアンタも助けてやるからよ」
「ッ……誰が、お前に」
「じゃあこのまま死ぬか?」
ハヴィルは青年の問いに拒否反応を示したが、やがて観念して渋々青年に機剏の使い方を口頭で教えた——
「——なるほどな。聞けば聞く程恐ろしい武器だ。この騒動を止めたらすぐに開発を停止させよう」
「ハッ……剏剣を、他人に使わせようとしていたヤツが、よく、言うぜェ……」
「無力な国家を相手に一方的に闘争を広げているお前らにだけは言われたくないね」
怪物が迫り来る短い時間の中、持ち前の理解力で機剏の扱いを会得した青年は、ハヴィルの嫌味を一蹴すると、単身バイオローグの群勢に立ち向かって行っ——「マ、待て……」
「ッ、何? まだ言い足りないことでも?」
「こ、こんな……ド真ん中に、俺を……置いておく気、かァ?」
「不満か?」
「当たり前ェだ……もしテメェが、一体でも取りこぼしたら、お陀仏……じゃねぇかァ」
「だったら机の下にでも隠れてろッ」
この期に及んで図々しいハヴィルのオーダーに耐え切れなくなった青年は、彼を部屋の隅へと蹴っ飛ばし、今度こそ単身バイオローグの群勢に立ち向かって行った。
そしてグロリアス・イブの発生から6時間後。事件はひとまず終息を迎える。景都の報道機関は当事件の推定被害者数を12万人、内生存者数を1人と報じた。事件の全貌は掴めていない。
◆
「……ん」
目を開けると、まず青年の視界に入ってきたのは白い天井だった。
無機質だが清潔感を感じるその天井に妙な心地良さを覚えながら、ここがどこかを考えようとするが、頭は霧がかったみたいに思考を遮っていて上手く働いてくれない。
やがて考えることを諦めた時、青年は漸く自分の全身を覆う拘束感に気がついた。特に口周りと右上半身。
まず口周り。どうやら口から鼻にかけてマスクのような物で覆われているらしい。その物質のせいか、呼吸をするたびに冷たく新鮮な空気が流れ込んできている。悪い気はしない。
そして右上半身。右肩から腕にかけて包帯で丁寧に手当てされたところに何やら細い管が繋がれていた。己の好奇心に従って管の行き先を目で辿ってみると、吊り下げられた透明な袋に行き着く。
袋の中は水のような液体で満たされており、時折、ぽつぽつと管の中に落ちては、腕を通して体内に染み渡っているようだった。
「目が覚めたか」
不調気味の頭でそこまでを認識すると、不意に左手の方角から声がしたので目を向ける。すると、堅苦しそうな黒一色の衣服に身を包んだ、恰幅の良い壮年の男がこちらを見据えて立っていた。
男が着ている衣服はまるで、上下ワンセットで着る為だけに仕立てたられたようなデザインで、統一感のある無駄のない、ピシッとした衣服だった。
「ここは……?」
「病院だ」
「ビョウ、イン?」
ビョウインとは何か? と困惑している青年を他所に、男は彼の頭上へ腕を伸ばすと何かを施すような動きをした。直後、小さな電子音が短く鳴り響くと、男は手持ち無沙汰になったのか、ポケットに手を差し込んで再度青年に話しかける。
「初めまして、俺の名は『神柳匠』検事をやっている」
「はあ」
カンナギと名乗るその男は、唐突に自己紹介をすると、ポケットから何やら妙に洗練されたデザインの小さな金属の塊を、青年の目の前に見せた。
それが何を意味しているのか青年にはよくわからない。特にくれるわけでもないらしい。金持ちアピールだろうか?
「今から半年前の8月31日。15時30分頃、鉱金駅構内で起こった事件について、君に事情聴取をしたくてここにいる」
「……それって今じゃなきゃダメなんですか?」
青年がくぐもった声でそう返答すると、男は黙り込んでしまい、規則的に流れる電子音を残して室内は静寂に包まれた。
ちなみに青年はさっきから会話の大半を理解できていない。だがしかし、それでもこの男の質疑応答に付き合うよりも、優先すべきことがあるくらいのことは本能的に分かっていた。
というか、そもそも身動きも取れない、明らかな重症人にする質問じゃないだろ。
「ダーハッハッ!! いやーすまんすまん。そうだよな治療が先だよな」
そして、この空間で大声を出して笑うことが御法度であることも何となく分かる。男は気にしていないが。
「いやー本当に失礼した。なにぶん景都史上稀に見ない最悪の事件だったからなー、気持ちが焦ってしまったよ」
もっと別の方に失礼したほうがいいと思うのだが、男はあくまで青年の返答に詫びると言葉を続ける。
「んじゃあ、とりあえず名前だけでも聞かせてくれないか? 病院に君の身元を伝えないといけないんだ」
そう言いながら男は鞄から飴色の手帳を取り出すと、今度は青年の方が言葉を失ってしまった。
「あり? それもNG? どのみちこの後ドクターからも同じ質問されると思うんだけどなー」
男も流石に想定外だったのか、一瞬困惑した表情を見せると腕を組みながら明後日の方向を見て考え込む。
「うーむ。俺が直接聴くのって結構レアなんだけどな……しょうがない、分かった。今、可愛い看護師さん連れて来るからちょっと待ってろ!」
「え!? いやちょちょ待て待て待て待て待て!?」
男の予想外の行動に青年は、自分の状態も忘れて声を張り上げて男を制止した。ついでに袖も掴もうとしたが流石にそれは届かず、空を掴む結果に終わる。
「ん? あーそうか、ナースコールしてたから呼びに行く必要は無かったな」
「いや、多分そういうことじゃないと思うんですけど」
「おいおい、っていうか君、ここは病院なんだから静かにしないと」
「アンタにだけは言われたくないわ!」
「ダハハ! 冗談だよ冗談。さて、場も暖まってきたところで」
——やかましいわ。っていうか冗談でもないだろ。
最後は酸欠気味になったので内心でツッコむ程度に留めておくと、青年はベッドに身体を預けて天井を見つめた。マスクから供給される空気が美味しい。
「で、どうした? 教えてくれる気になったか」
「あー、はい。えっと……その」
男は定位置に戻ると、ベッドの横にあった丸椅子に腰掛け手帳を開く。
「おう、何でも聴くぞ」
その男の発するドカっとしたオーラに、青年は「えもいわれぬ安心感」を覚えると、意を決して口を開いた。
「僕は……誰なんでしょう?」
青年は記憶を失っていた。
それは景都を狙う脅威が未だ去っていない中、その正体や抗う術を知る者が誰一人としていなくなったことを意味していた。