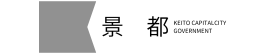「結論から申し上げると逆行性健忘と解離性健忘を併発していると考えられますな」
「ぎゃっk……へ、何て?」
「ギャッコウセイケンボウとカイリセイケンボウ。いわゆる『記憶喪失』ですな」
そう告げたのは、井ノ頭と書かれた名札を付けた白髪交じりの医師だ。親とはぐれた子鹿のように困惑している様子の青年に諭すように説明した。
「して、どのくらいの期間の記憶が抜けているんですかい?」
と、尋ねたのは、青年の傍で仁王立ちで立っている壮年の男「神柳匠」だ。ケンジという仕事をしているらしく、今日も初対面と同じ堅苦しそうな上下一揃いの黒い衣服に身を包んでいる。
この男達がいるのは大都会景都の中心も中心。景都大学附属病院の2階、外来診療棟にある脳神経内科の診察室である。
「ふむ……」
神柳の問いに井ノ頭は、すぐには答えず一度青年の方へ目を向けた。そして彼が首肯したのを確認すると、電子カルテに目を移しつつまったりとした口調で答え始めた。
「現時点での検査結果から判断すると、最後に意識を失った半年前から以前の記憶が抜け落ちていますな。また、自身の名前や年齢、職業といった個人的な情報や、人間関係に関する記憶も残っていませんな。 ただし、読み書きや計算といった基本的な知識は残っているので、日常生活に必要な最低限の動作は行えると考えられますな」
「ってことは事件当時の記憶もサッパリ、か……」
井ノ頭の回答を受けて神柳が腕を組みながらそう呟く。しかし井ノ頭はそれには触れずに聞き流し、そのまま患者である青年に今後の見通しを伝える。
「今後の治療方針としては、定期的に診察を受けてもらいながら、心理療法やカウンセリングを通じて精神的な負担を軽減していくところから始めましょうな」
「は、はあ」
対する青年はあまりの情報量に圧倒され、医師の言葉にただ頷くことしかできなかった。
「ここまでで何か質問はありますかな?」
「え、えぇ……質問って言われったってちょっと急すぎて思いつかないっていうか、質問を生み出す為の情報が無いっていうか……」
不意に医師から投げ掛けられた逆質問に青年は言葉を詰まらせる。するとそこに神柳が割り込む。
「じゃあ、俺から聞く。この子の記憶は"いつ"戻るんだ?」
神柳の躊躇ない割り込みに井ノ頭は「えぇ、あなたが?」と言わんばかりの顔をしたが、やがて疎ましながらも渋々応じた。
「"いつ"と言われましても、そもそも100%戻るとも言い切れませんな」
「なっ、じゃあせめて一番新しい半年前の記憶だけでも良いから呼び起こす療法とか無いのか?」
「そんな都合の良い治療方法なんてあるわけないですな」
そう言って井ノ頭は、神柳の無理な要望をピシャリと切り捨てた。その言葉には若干棘があるかのように青年は感じていた。
「そりゃねぇぜ……ドクター」
対する神柳は、医師の感情など一切察していないかのように落胆してため息を吐く。どうやらこの男は人の気持ちにはあまり頓着しないらしい。
医師も神柳がそういうタイプの人間なんだと分かったのだろう。軽く頭を振ると、今度は逆に神柳へ問い掛ける。
「ところで、彼の身元について検察側の捜査結果もお聞かせ願えますかな?」
「ん、ああ……そうだな」
医師の言葉を受けてから少し思考を巡らせているかのような仕草をしていた神柳は、一瞬バツの悪そうな顔をするも、すぐに捜査結果の報告を始めた。
「検察の方でも彼が病院に搬送されてから今日に至るまでの約半年間、警察と協力して国内外のデータベースを元に指紋・DNA・顔照合と行った」
「そんなことしてくれてたんですか?」
神柳の思いもよらぬ発言に青年も思わず口を挟む。
「して、結果は?」
「……残念ながら現状身元特定には至っていない状態だ」
「なんと! 検察と警察が総力を上げてもですかな」
「えぇ、恥ずかしながら」
「とはいえ、捜査を経て何かしらの仮説は立っているのではないですかな?」
「……ズケズケと聞くなぁ」
「どうされましたかな?」
「いえ、何も」
井ノ頭の耳には聞こえていなかったみたいだが、青年の耳には確かに神柳の吐いた悪態が聞こえていた。というか寧ろ、青年に愚痴るつもりで言ったのだろう。
神柳はゴホンと一つ咳払いをしてから問いに答える。
「あくまでも検察の見解だが、少なくとも彼がこの国の人間である可能性は低いと考えている」
「と、すると?」
「……外国籍または無国籍の人間ではないかと推測している」
そこまで言い切った神柳の顔は、苦い粉薬を飲まされたかのような顔をしていた。恐らく口外したくない情報だったのだろう。
「マジでここだけの話にしといてくださいよ。先生」
「あい、分かってますとも。医者の口は病院のベッドよりも硬いので安心せい」
「若干安心できない例えなんですけど」
そこまで言うと、二人の間で話すことはひとまず尽きたのか、診察室の中はさっきと打って変わって沈黙に包まれた。
「あ、あのー」
その空気を察した青年はここぞとばかりに漸く口を開いた。
「お、質問ですかな?」
「えぇ、まあ。ちょっと気になったことがあって」
「いいぜ、なんでも言ってみろ」
「あなたは極力静かにしていてほしいんですな」
医者の毒を含んだ言葉に神柳が何かツッコミを入れようとしていたが、青年はそれを封殺するかのように、頭に浮かんだ純粋な疑問を即座に二人に投げ掛けた。
「えっと……! なんでこんなに手厚く保護をしてくれるんですか? この国の人間ならまだしも、僕はそれらに該当しない人間だというのに」
「そ、それはですな……」
青年の疑問はもっともだった。身元も国籍も不明な人間に、ここまで手厚い保護が施されるのは異例中の異例だ。
通常なら、せいぜい身柄を確保されたまま、行き場もなく施設に留め置かれるのが関の山だろう。
そんな青年の鋭い質問に井ノ頭は回答に困っていた。できれば言いたくない。彼の精神に支障を来たしかねない内情だったからだ。
しかし、医師の思いは叶わない。"この男"が"ここ"にいる限り。
「なんでって、そりゃあお前が6ヶ月前に起きた事件の重要参考人だからだ」
「じゅ、ジュウヨウサンコウニン?」
「あなたって人は……全く」
躊躇いひとつない神柳の一言に、医師は額に手を当てた。